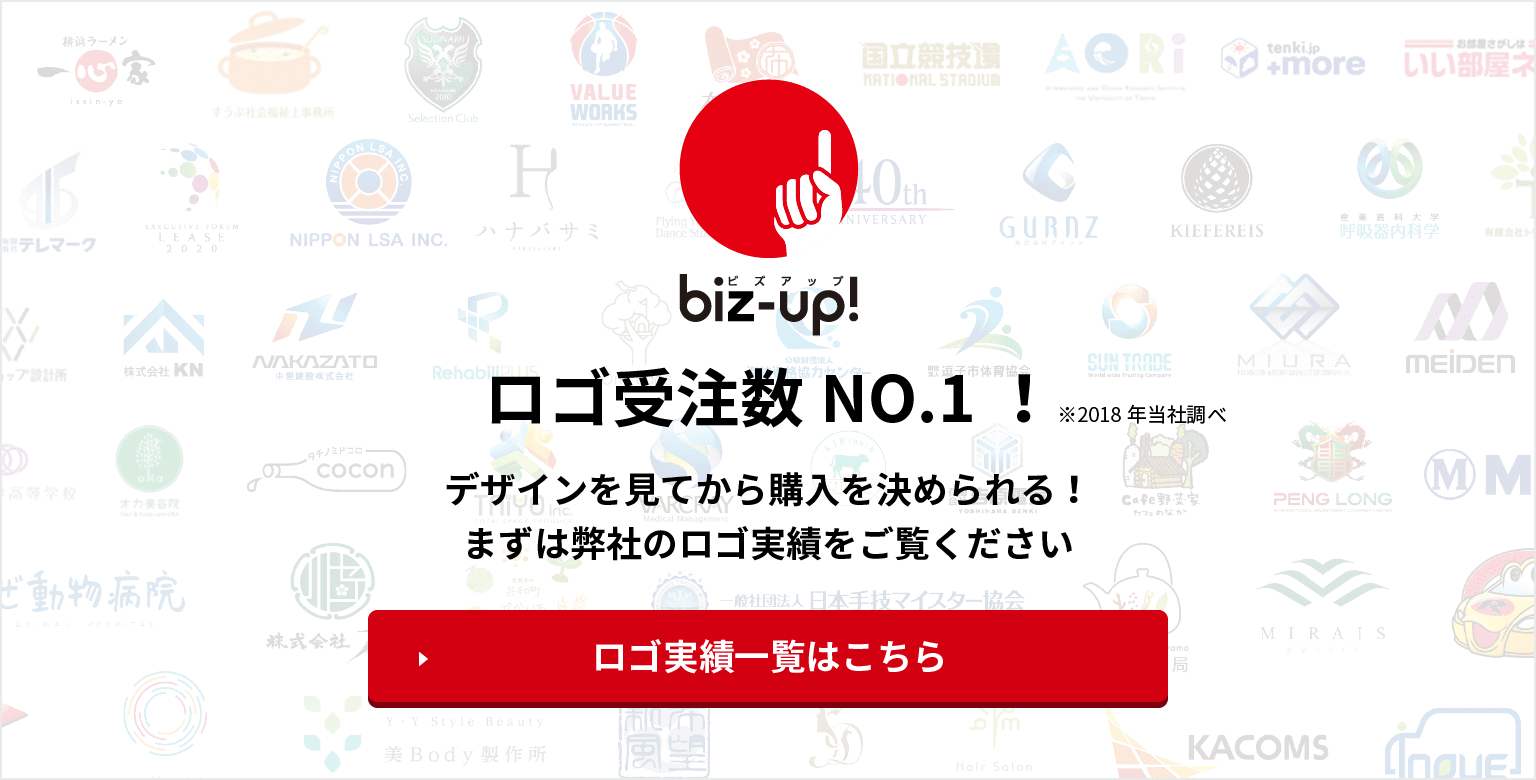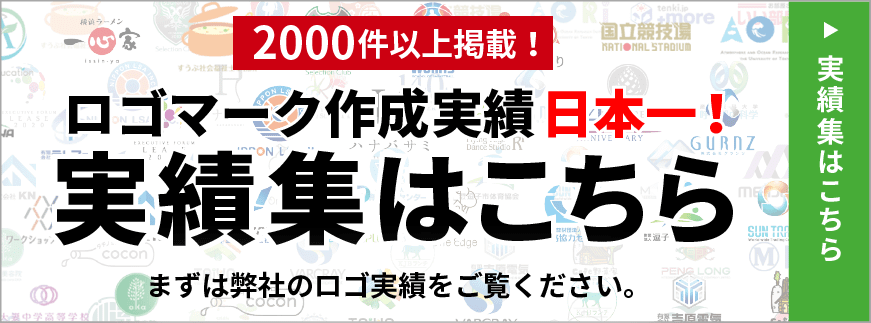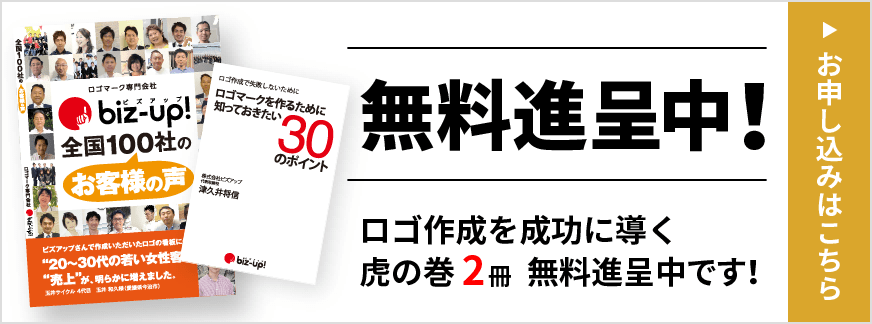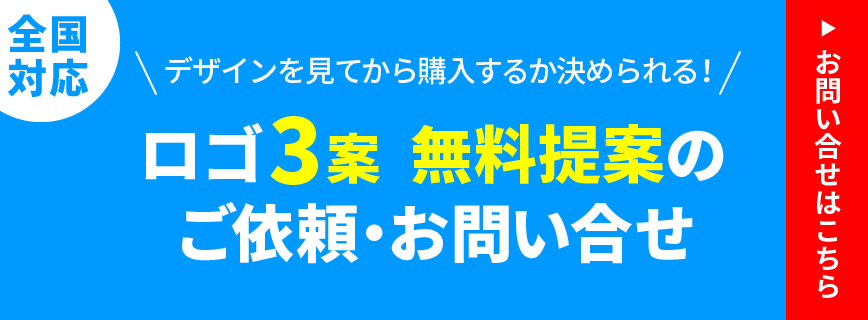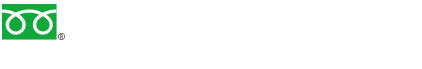ロゴコラムLogo column
4月も終わりが近づいてきました。4月が終わるともう2025年も3分の1が終わることになります。早いなー。
最近ですが、よく読んでいる著者の本があります。私はけっこうハマると同じ著者の本を何冊も読む傾向があるのですが、今回もそうなりそう。
過去には以下のような人々の本にハマりました。
- 神田昌典
- 金森重樹
- 伊吹卓(私の師匠です)
- 苫米地英人
- 小山昇
- 石原明
- アル・ライズ
他にも誰かいたような気がするのですが、思い出せません。
かんたんにいえば、私はこれらの著者のファンだといえます。そして「最近よく読んでいる著者」と言いましたが、新しくファンになりそうなのが、東証プライム上場企業「北の達人コーポレーション」の木下勝寿さんです。
北の達人は北海道の特産品をメインとした通販会社です。主にWebマーケティングを駆使して事業を行っています。
今のところ木下さんの本は3冊買っており、2冊読み終わりました。
- チームX(エックス) ── ストーリーで学ぶ1年で業績を13倍にしたチームのつくり方
- 売上最小化、利益最大化の法則 ── 利益率29%経営の秘密
- 時間最短化、成果最大化の法則 ── 1日1話インストールする“できる人”の思考アルゴリズム
3つ目はこれから読むところです。
木下さんの本は難しい内容が非常にわかりやすく伝わりやすく書かれていて、自分だけでなく社員にも読ませられる、読ませたいと感じます。
しかも超親近感を持ったのですが、なんと木下さんの本の中には師匠である伊吹先生が登場するのです。
本での書き方から察するに、おそらくお会いしたことはないのではないかなと思うのですが、伊吹先生の理論を北の達人の中でも活用しているということで、なんだかうれしかったです。
さて、そんな木下さんの本の中に「ファン」について面白い記述がありましたので、それを絡めて本日は「ファン」についてのお話。
●ファンとブランディングの関係とは?
「ブランディングとは?」と聞くと、ある一定の人たちがこのように言います。
- 「ファン化することです」
これは間違いではないのですが、これだけでは「足りない」ということになります。
「ファン化」とは何かというお話をするために、まずはブランディングの概要をお伝えしたいと思います。
ブランディングにはステップ(階層)があります。そのステップは次のようなものになります。

まず、「知られる・知られている」というフェーズがあり、次に「理解される・理解されている」というフェーズがあります。つづいて「記憶されている」というフェーズがあり、ここまではまだ消費者に購買経験がない状態。
つづいて、購入してもらい、「リピーター化」という再購入してもらうフェーズが来ます。最後に「ファン化」となります。
そうです。「ファン化」はブランディングの中でも最後に出てくるだけなのです。
そもそも、「知らない」状態ならファン化もクソもありません(汚い言葉使いが出ました、失礼)。知らない人、知らないもののファンになることは不可能です。当たり前ですね。知って、やっとはじめの一歩を踏み出します。
知ったあとに、それについてもっと詳しく知りたくなります。理解しようとします。この商品や商品をつくっているメーカーはどんな会社なんだろう?このアイドルはどんなコンセプトのアイドルでどんなメンバーがいるんだろう、などですね。
ここで、次の階層に行くうえで「タイミングを問う商材かどうか」が関わってきます。
タイミングを問う商材とは、たとえば我々のロゴなどもそうですし、家とかもそうですね。他にもいっぱいありますが、知って「すぐに買おう」とはならない商材です。ほしいと思って買うというより、必要性がでてきたときに買う、必要なタイミングが来たら買う、という商材。
タイミングを問う商材の場合、そのタイミングが来るまで記憶していてもらうことが大切になります。すぐに買ってもらえないわけですから、それまでいかに覚えていてもらうか、タイミングが訪れたときに一番に思い出してもらえるか、ということですね。
逆にタイミングを問わない商材というのは、ニーズよりウォンツで購入されるものです。お菓子とか。洋服とかも。まあ洋服もスーツとかになるとタイミングが問われるケースもあるんですけどね(入学式、成人式、就活、新社会人など)。衝動買いできるものなどもこれ。
なので、ウォンツで購入される商材の場合は、知ってすぐに購入(=体験)、または知って理解してすぐに購入(=体験)となるケースもかなりの割合であるということです。「記憶される」をすっ飛ばす場合があるということです。
そして次の階層が「リピーター化」です。一度商品を体験し、また継続したいかどうか、ということです。これをつづけているうちに、一部の人がファン化する、というわけです。
リピート性のない商材の場合、ここを飛ばしてファン化する場合があります。家とかはあまりリピートされる商材ではないですよね。
一連の流れをアイドルグループなどに置き換えて見るならば、
- アイドルのことを知り
- 調べてみて(理解し)
- CDを買ってみるとかyoutubeで動画を見るとかライブに行くとかで体験し
- そしてまたそれらの活動をつづけたいと思い
- つづけているうちにいつのまにかファンになっている
こんな流れです。美容室とかであれば、
- その美容室のことを知り
- ネットとかで調べて
- 1回利用してみようということで体験し
- また来月も来たいと思い
- つづけているうちにファン化する
ということです。
ちなみに、商品によっては「ファン化」しないものもあります。これは「不安払拭型ブランディング」を行っている商材の場合に起こりがちです。
たとえば、「乾電池」とかはどうでしょう。パナソニックのアルカリ乾電池が好きすぎて興奮する、ないと寝られない、みたいな熱狂的な人はちょっと想像しづらいですよね(電池マニアとかでいるかもですが笑)。
こういった場合、リピーター化まではいってもファン化はしません。これは乾電池の購入プロセスが「不安払拭型」だからです。加点方式ではなく減点方式、成功したいのではなく失敗したくないというモチベーションで購入するためです。
不安払拭型ブランディングの代表例は「チェーン店」です。チェーン店に求めるのはサプライズや高品質ではなく、「どこでも同じ」、「失敗しない」です。
こういう商材はファン化しづらいです。ファミレスの「デニーズ」が好きすぎて通い詰めるという人は、いるかもしれませんが多くはないですよね。
なお、強烈なブランディングができているブランドだと、商品の購入(=体験)がない状態でもすでにファンがいます。
たとえばバイクとかどうでしょう。ハーレー・ダビッドソンなど。ハーレー購入者はハーレーを買う前からハーレーのファンという人が一定数います。「知られて」「理解される」だけでもファンづくりが可能だということを指し示しています。
- ハーレーのことを知り
- ハーレーのことを調べて理解しファンになる
- 「いつか乗りたい」と夢見つづけ(記憶し)ついに購入
- 数台持ちできるようなお金持ちではないのでリピートはできない
- けれど1台を大切に乗りつづけ、ずっとハーレーのファンでいつづけている
こんなパターンもあるということです。
●なぜファン化を目指すべきなのか?
では、ファン化すると何がうれしいのでしょうか?
「チヤホヤされる」のがうれしいという人もいそうです(笑)。ファン化の対象が「人」の場合、たとえば芸能人とかの場合、チヤホヤされてますものね。私もチヤホヤされたい(爆)。
ファン化すると何がうれしいのか、これは、広告費をはじめとした顧客獲得コストを圧倒的に圧縮できるということに尽きるかもしれません。
ファンは裏切りません。よその競合商品に目移りしません。リピートしつづけてくれます。また、ファンが多ければ多いほど、口コミなどが発生しやすくなることは想像に難くないでしょう。
こういった点から、ビジネスにおいてのファン化の最大の功績は、「チヤホヤされる」ではなく(笑)、顧客獲得コストの圧倒的圧縮といえるわけです。
ちなみに、新規とリピートだと顧客獲得コストがどのくらい違うか、ご存知ですか?
「顧客獲得コスト」とは、お客さんを1件獲得するのにかかるコストのことです。
通販会社などはわかりやすいです。お客さんにまず知ってもらうためにリストを集めます。このリスト集めにかかる費用というものがまずあります。
つづいて、お客さんに理解してもらうためにチラシや冊子、資料などを配ります。ここでも印刷コストや配送コストという費用がかかります。
こうしてそれらを受け取った人の中の一部がお客さんになるわけです。
たとえば100人分のリストを集めるのに10,000円かかったとします。そして100人に冊子を配るのにかかった印刷コストや配送コストが20,000円だったとします。つまり事前にかかったコストは30,000円。
で、100人のうち10人が商品を購入しお客さんになってくれたとします。そうすると、顧客獲得コストは[30,000円÷10人]となり、3,000円となります。
もしもひとつの商品の粗利益が5,000円だったとしたら、[5,000円−3,000円]で、顧客獲得コストを除いた利益は2,000円です。10人なら20,000円。
口コミなどによりこの顧客獲得コストが10分の1ですんだとしたら、利益は47,000円となり、倍以上違うわけです。手残りがぜんぜん違う。
もちろん、ファンさえいれば広告費やプロモーション費用がまったくかからなくなるというわけではありません。
しかし、想像してみてください。ファンの誰かから商品についてポジティブな口コミをもらっていたときと、ファンから何も話を聞いていないとき。比べたら、プロモーション費用1円あたりが生み出してくれる効果には、かなり大きな違いがありそうではないですか?
ちなみに「ファン」と「リピーター」だと少し違ってはきますが、参考になる指標として、「1:5の法則」というものがあります。
これは、新規の顧客から何かを買ってもらおうとするときにかかるプロモーション費用と、リピーターさんから再購入してもらおうとするときにかかるプロモーション費用とでは、5倍の開きがあるというものです。そのくらい新規顧客の獲得にはコストがかかるんだよ、ということです。
私の友人でリピーターコンサルタントの一圓克彦氏はこれについて懐疑的でした。そして、「いくらなんでも5倍も違うわけないやろ!」ということで自分で調べたそうです。
そうしたら11倍だったらしいです(笑)。
11倍ものお金をかけて新規の顧客を獲得しているわけだから、1回のお付き合いで終わってしまうのは非常にもったいないわけです。一度お客さんになってもらったら、何度もリピートしてもうことを目指すべきなんですね。
しかしながら、リピーターコンサルタントの一圓さんも「リピーターだからといってファンとは限らない」と言っています。それだけファンは貴重な存在。
ファンはビジネスにおいては、いうなれば「無償ではたらいてくれる御社の営業マン」と同じです。こんな貴重でありがたい方々、なかなかいないわけです。
●ファンのつくり方
では、どうすればファンをつくることができるのでしょうか。
これに関してはとても難しい。私もまだ研究中で答えがわかりません。しかし、冒頭でご紹介した木下さんの本に面白い事例が載っていました。
ひとつは「演歌歌手3,000人の法則」です。
本によると、「演歌歌手は3,000人と握手をしたら一生食べていける」と言われているそうです。木下さんは、昔見たランキング形式の音楽番組で知らない演歌がランクインしている理由がこれでわかったと言います。
北の達人がある北海道出身のミュージシャンはこれを実践している人が多そうだとも語っていて、北島三郎や細川たかしなどの演歌歌手のみならず、松山千春や中島みゆきもそうではないかと木下さんは考察しています。
また、同じように北海道出身のロックバンド「GLAY」は、今では自分たちでファンクラブを運営しているそうです。彼らはファンの誕生日にボーカルのTERU自らファンにメッセージを送っているそうです(そういう時間を必ず1日30分設けているんだそう)。
これはファンの対象が「人」の場合には有効そうです。ここでキーワードになってくるのが「距離感」ではないでしょうか。遠いようで近く、近いようで遠い存在。「好き」とも少し違う感覚。
ヨメのことを「ヨメのファン」という人はあまりいないですよね(そういう人を何人か知っていますが笑)。ヨメは距離が近すぎるし、好きだとしてもファン心理とは違う。
では、アーティストや芸能人のように実在する人ではなく、実在しない人(?)だったらどうでしょう?距離感としてはMAXで遠いわけです。
これは宗教(神様)なんかがそうかも知れません。宗教は、ある意味「その神様のファン」と言い換えても良さそうですよね。
では、実在するかもわからない、見たこともない人(?)の何に惹かれてファンになるのでしょうか?
私は、それは「why」だと考えます。
「ファン化」、特に「どうすればファンがつくれるか?」は非常に言語化しづらい分野ですが、その理由はこの「why」に関係しているからだと私は、考えます。
「why」とは、私の心の師匠サイモン・シネック氏が提唱する「ゴールデンサークル」という理論に出てくるものです。
ゴールデンサークルは、「why」「how」「what」の3つの同心円からできています。
たとえば、何かの商品を売りたいときに多くの人が「what」から説明してしまいます。「こんな商品です」「他社より優れた商品です」「こんな機能がついています」など。
サイモン・シネックはこれでは売れないといいます。
対して、多くの世界を変えた起業や人は、何かを語るとき、すべからく「why」から話しはじめるのだそうです。
たとえばAppleなら、
- わたしたちのやることは、世界を変えられると信じている(why)
- 世界を変える方法は、美しいデザインで、かつ直感的に使える、今までにないデバイスだ(how)
- その結果、このような製品ができあがった(what)
となるわけです。
この「why」は人間の脳の構造上、言語化しづらいです。なぜか。
ゴールデンサークルは、サイモン・シネックがいうのは脳の構造とリンクしているそうです。「why」は人間の脳でいえば中心に近く、人間が言葉を扱いはじめるよりももっと前からある「大脳辺縁系」にあたります。対して「what」は人間が言葉を司るようになってから発達したと言われる「大脳新皮質」で、これは脳の外側にあります。
人間の脳は当然ながら言葉を扱いはじめる前から存在し、言葉を扱いはじめる前から感情があります。つまり、「why」は人間が言葉を扱いはじめる前からある感情に紐づいているから、すべてを言語化するのが難しいわけです。
そして、「ファン」や「ファン化」が言語化しづらいのも、これらが「why」と大きく関係するからです。
先ほど宗教に例えましたが、宗教であれば「why」が教義となります。その教義のファンが信者です。アーティストだって同じようなものです。そのアーティストの見た目、話し方、考え方、芸術性などを総合した「人間性」という「why」が人を引き付けます。
ではビジネスにおいては「why」は何でしょう?
ひとことでわかりやすくいうならば「想い」と言ったところでしょう。「なぜそのビジネスをしているのか?」「なぜその商品を開発したのか?」を知ってもらい、共感してもらえたときに、ファンができるのではないかと考えます。
ちょっと話が飛びますが、我々は「言葉のデザイン」も行います。たとえば経営理念やビジョン、行動指針などの言語化も行いますし、ネーミングも行います。
その中で「タグライン作成」というサービスがあります。
「タグライン」とはなにかというと、超平たくいうとキャッチコピーの一種です。では、「キャッチコピー」と言ってはなぜダメなのか。
キャッチコピーとは、日本語で言うならば「惹句(じゃっく)」となります。惹きつけるコピー。競合他社との違いや自社の強みを表現することがメインです。つまり、その目的は「商品販売」です。商品を売るためのコピーがキャッチコピー。
対してタグラインは何かというと、「ファンをつくるためのコピー」となります。
たとえば私が好きなタグラインに、大成建設の「地図に残る仕事」というものがあります。これは、大成建設の強みや競合との違いには言及していません。しかし心にグッと来るコピーです。同じ建設業界に入社するなら大成建設に入社したい、こう思った人は多いのではないかと私は考えます。
さて、「ファン」「ファン化」についてお話をしてきましたがいかがでしたでしょうか。かなり抽象度の高い小難しい話になってしまったかもしれません。
御社もファンをつくる活動をしてみませんか?ぜひビズアップにお手伝いさせてください。
今回はここまでです!
津久井
投稿者プロフィール
-
ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。
かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。
2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。
最新の投稿
 カテゴリ一覧
カテゴリ一覧
 関連記事
関連記事
ご依頼・ご相談・
各種お問い合わせは
こちらです
インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。
-
フォームからのご依頼・
お問い合わせ24時間受付中